
先輩たちの声
東京⼤学⼯学部航空宇宙⼯学科は1920年の設⽴以来、航空及び宇宙⼯学の教育と研究において重要な役割を果たしてきました。この長い歴史の中で、学科から3,000名を超える卒業⽣を輩出し、国内外を問わず航空宇宙分野を含む様々な分野でリーダーシップを発揮しています。
OB/OGのメッセージ
東京大学航空宇宙工学科で活躍する先輩たち
2024年度
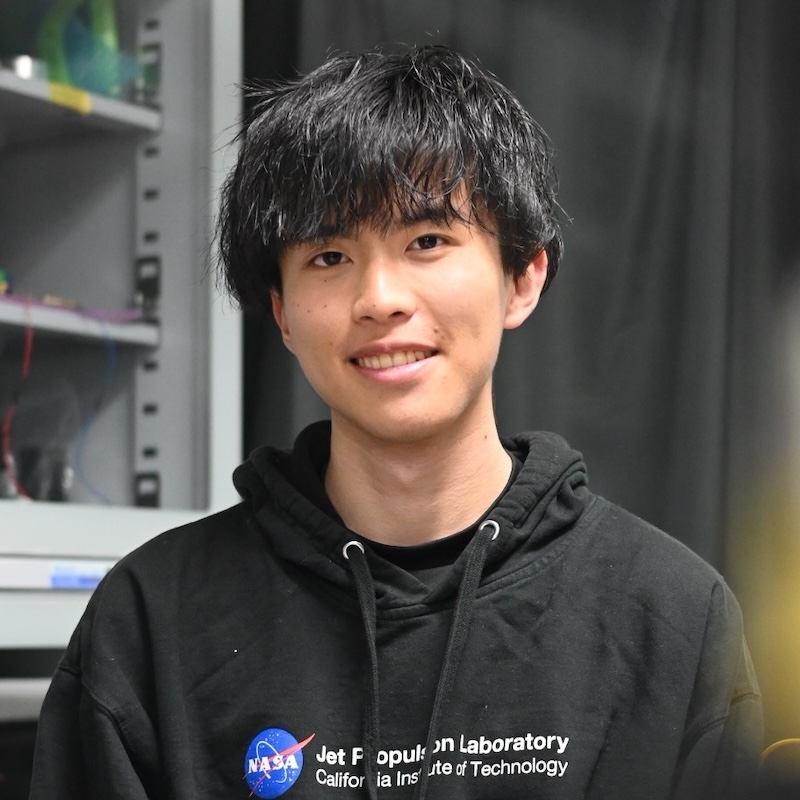
私はなんとなく宇宙が好きだからという軽い気持ちで航空宇宙工学科に進学をしました。しかし、航空宇宙工学科での充実した日々は、自分をもっと"宇宙好き"にさせてくれました。どの工学分野でも通用する工学基礎の知識から、航空宇宙特有の学問まで幅広く網羅する講義は言うまでもなく魅力的でしたが、航空宇宙の最前線を戦っている方々の貴重な経験をお聞き出来たり、実際に開発を行う機会が豊富にあるということも、航空宇宙工学科にしかない長所だと感じます。なんとなく好きで飛び込んだこの分野でしたが、現在は研究室で人工衛星の開発と運用を行いながら、光の干渉と衛星の精密な制御を組み合わせた研究に没頭しています。最先端の研究、開発の幅広い経験と、ともに高めあえる仲間を得ることができ、心から航空宇宙工学科を選んでよかったと感じています。
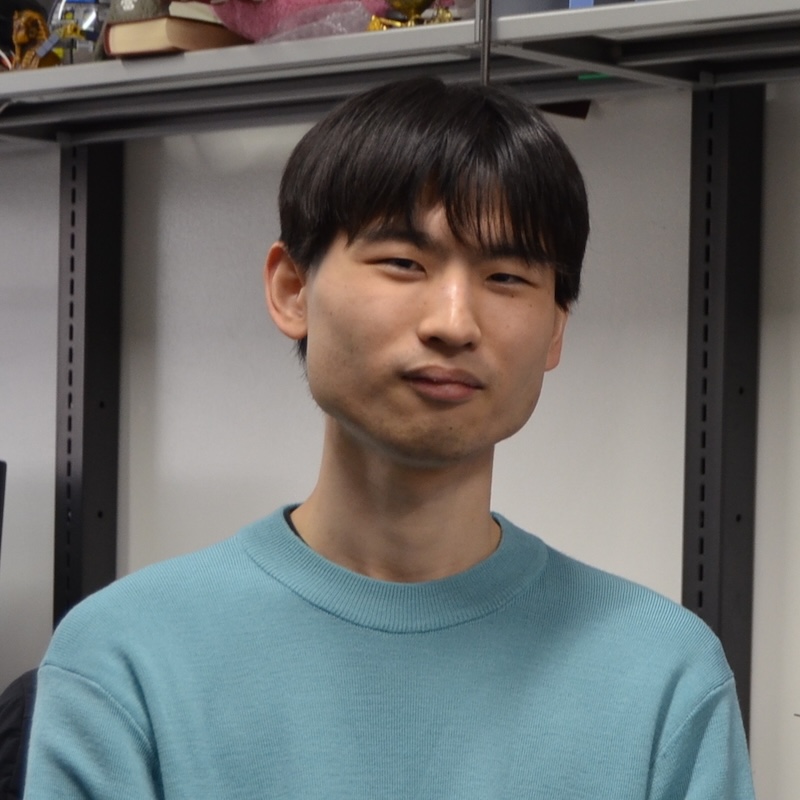
小さい頃から飛行機に興味があり、この学科に進学しました。本学科では、授業で航空宇宙工学に関する基本的な知識を幅広く習得できるだけでなく、実際に自分でものを作る機会が豊富に与えられています。私は2年生の時に迷路探索ロボットを作り、ロボット制御の基礎を学びました。3年生の時には固定翼機を設計し、飛行させました。卒業研究ではこれらの経験を活かしてマルチコプタを飛行させ、自分で導いた理論の有効性を実証しました。自分が手掛けたものが飛んでいく瞬間には筆舌に尽くし難い感動を覚えます。こうした活動では授業で学んだ飛行力学や構造力学、空気力学などを使って考えていきます。このように授業と実践的活動が学習の両輪をなし、より興味を持って航空宇宙工学を学ぶことができます。

大学入学以前からの希望通り、航空宇宙工学専攻に進学しました。海外での研究に関心があり、国際色豊かな研究室に所属することに決めました。研究室では、スパコンを駆使し、航空機の翼の現象の解明及び解明のための手法に関する研究を行いました。この研究を進める中で様々な困難に直面しましたが、結果が得られたときには得難い喜びがありました。また、それらの結果を国内外での学会や論文等で発表することで、多様な研究者達と交流できたことが自身の成長につながっていると実感しています。航空宇宙工学専攻では経済的支援や海外留学のための奨学金が充実しています。国際的視野から研究できる優れた環境や支援体制のおかげで研究に集中できるとともに大変励みになりました。

専門性を磨きながらも、多様な課題に挑戦できる点が本専攻の大きな魅力です。
博士課程では、リブレットと呼ばれる空気抵抗低減デバイスの航空機への適用を目的とした数値解析や、大気球を用いた火星探査航空機の実験に取り組みました。
試行錯誤の連続でしたが、その過程で専門性が磨かれていくのを実感しました。
さらに、本専攻では海外の研究者との交流や国際学会での発表の機会も多く、航空宇宙工学が真に国際的な分野であることを肌で感じる場面が多々ありました。
異なる文化で育った人々の価値観に触れることで、多様な視点を尊重する姿勢も養われます。ここでは専門性を磨くだけでなく、人としての成長も実感できます。
2023年度

小学生時代に模型飛行機を作って飛ばしたことがきっかけで、飛行機に強い興味関心を抱くようになりました。学部の授業では知識の習得だけでなく、工学的なセンスも磨かれる講義も多く、私にとって非常に刺激的な日々でした。卒業研究では、高校時代の探究活動を深めるべく楕円環状翼機の概念設計を行いました。学科の授業で学んだ空気力学や構造解析の知識を用いて翼形状を最適化し、実機レベルでの成立性を示すことができました。これで東京大学に推薦入学した目的が達成できたので満足しています。恩師や仲間に恵まれた航空宇宙工学科での2年間を糧に、大学院での複合材研究にも取り組んでいきたいです。

私は前期教養で学んだ熱力学をきっかけにエンジンに興味を持ち、航空宇宙工学科に進学しました。この学科では多岐にわたる工学分野を学ぶことができ、それらの知識を統合して具体的な形を生み出す機会も豊富にあります。卒業論文では航空機エンジンの騒音をテーマに実験、解析、考察を行いました。卒業設計では課題や仕様の設定から始め、サイクル最適化、空力設計、製図までを手がけ、自らのエンジンを完成させました。先生方や先輩方からのご助言や同期との知識の共有を通じ、理解を深めたり新しい視点を得たりすることができました。優秀で意欲的な同期と共に過ごす中で航空宇宙への貢献に対するモチベーションを高め、私の学部生活は充実したものとなりました。

幅広い選択肢から宇宙開発への関わり方を選びたいと考え、ハードからソフトに至るまで多様な分野を学ぶことが出来る航空宇宙工学科を選びました。大学院ではJAXA宇宙科学研究所の研究室に所属し、宇宙機用熱制御デバイス内での物理現象解明を目的とした研究をしています。宇宙環境を模擬した実験は制約が多く大変ですが、頭と手をたくさん使うので学びも非常に大きいです。大規模な宇宙探査プロジェクトが身近で動いているため、自分の研究が宇宙開発にどのように貢献できるかイメージしやすいのも魅力の一つです。基礎研究を行っている研究室から実際に衛星を開発している研究室まで幅広い選択肢があるので興味のある分野がきっと見つかると思います。

これまで航空宇宙工学科で研究を行ってきた中で感じることは、数値計算、解析、実験、ものづくり、どれにおいても、新しいものを具現化することがいかに難しいか、ということです。
私は、この困難を知ることが、新たな専門知識や技能を身につける動機となり、より良い研究につながると考えています。私自身も、小天体探査に関する研究を行う中で、壁にぶつかりながら、専門性を高め、成長できました。
航空宇宙工学科では、卒業論文・卒業設計を含めた授業によって、何かを作る難しさとその乗り越え方を学べると思います。加えて、将来こうなりたいと思う先輩にも多く出会えたことからも、この学科を選んで良かったと感じています。



